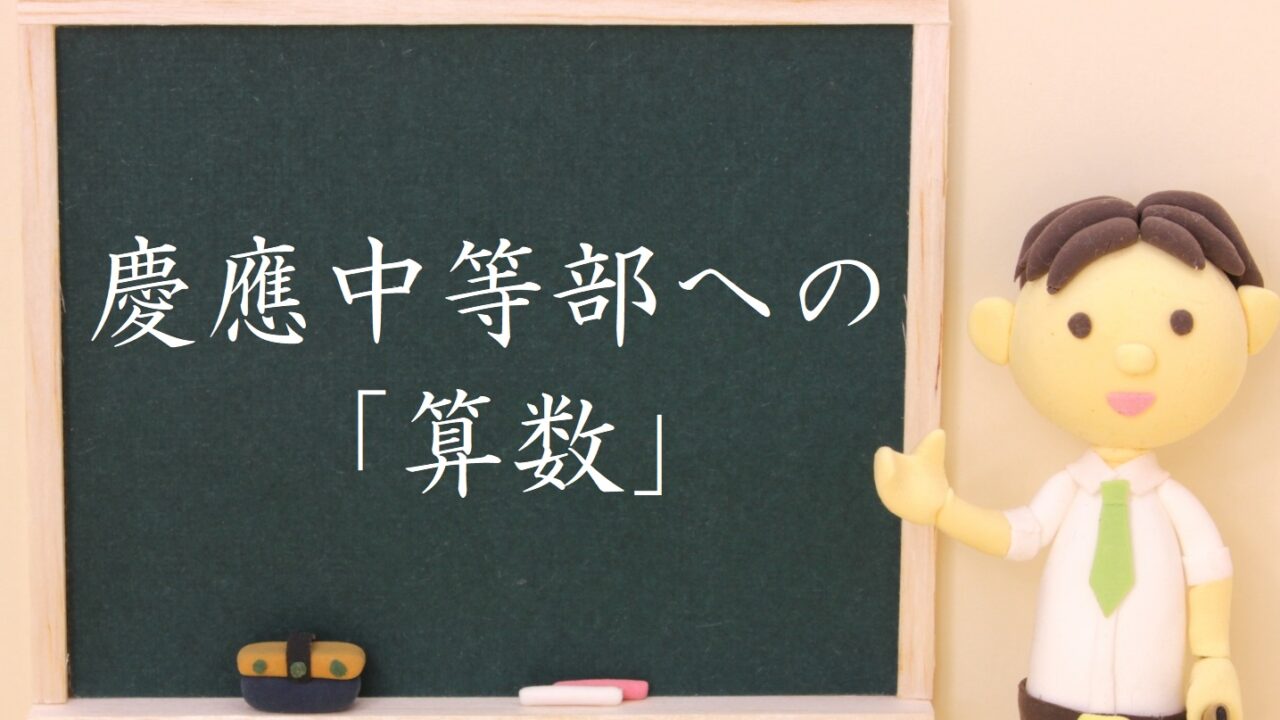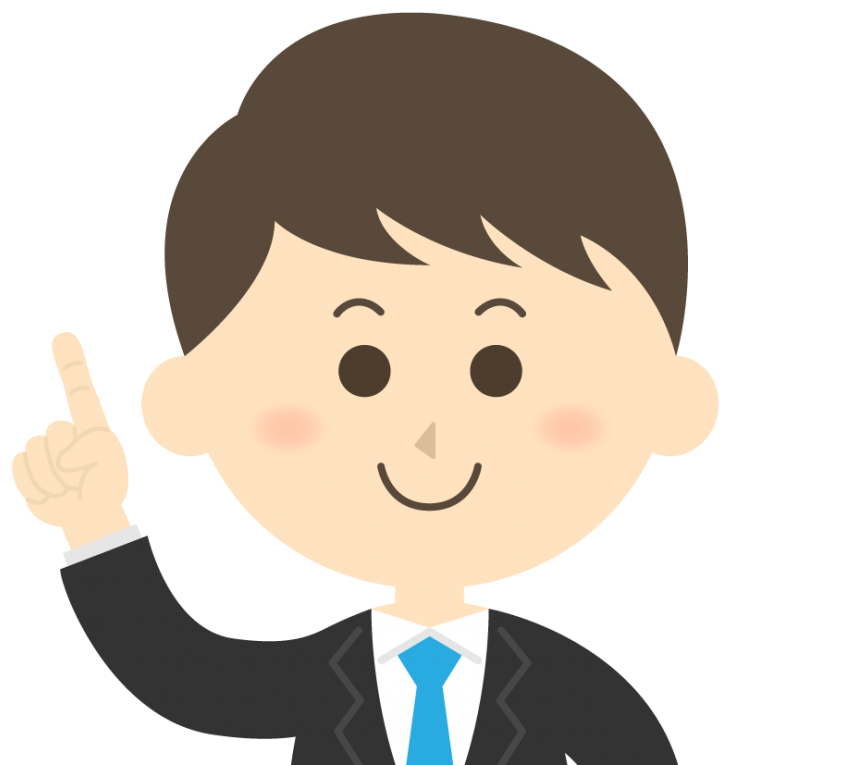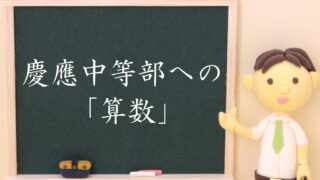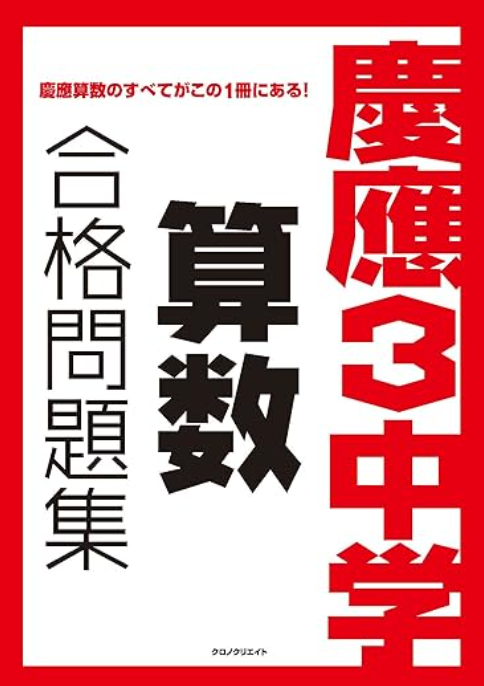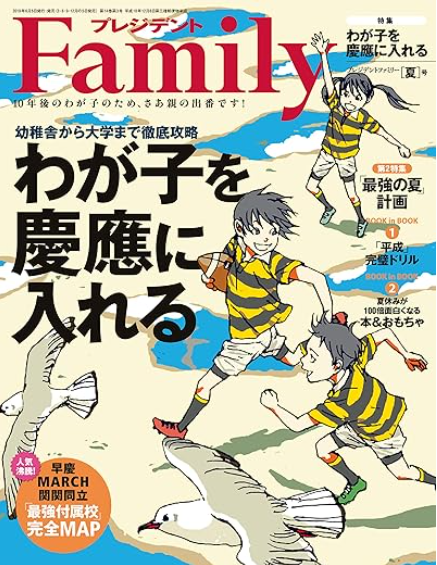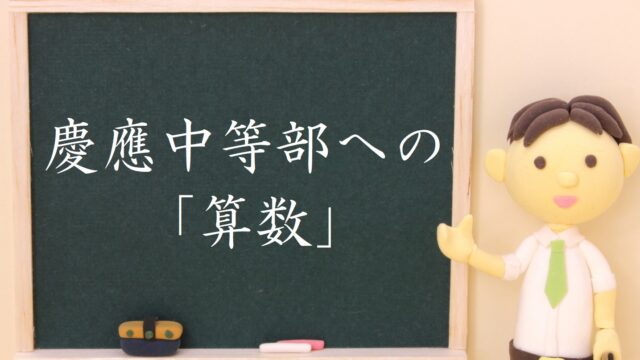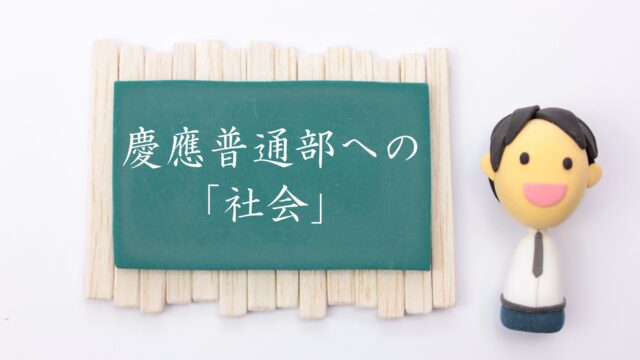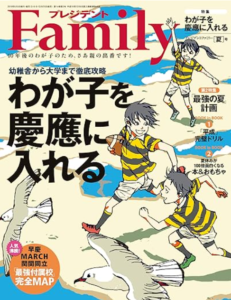このブログは、慶應付属中専門の塾講師・家庭教師をしているたくと( @tact_roadtokeio ) がお送りしております。
さて、今回は「慶應義塾中等部の算数」について。いよいよ科目ごとに見ていきます。
これまで長く指導してきて、直前期に助けを求めてご連絡くださるご家庭で最も多い内容が、この「慶應中等部の算数」についてです。
慶應中等部の算数については、本当に誤解が多い。そして受験生や親御さんに誤解が多いのは理解できるけど、塾の先生・家庭教師の先生が誤解していることが多いのが、上記の「直前期に求める助け」に直結しているように感じています。そして直前期だと手遅れになってしまうことも多い。
というわけで、今回はそんな誤解の多い慶應中等部算数の「構造」を見ていきます。(この「構造の見誤り」が先述の誤解の主因になっているからです。)
慶應中等部を志望する受験生・親御さん、なんなら指導している先生方もぜひ読んで見てください。
では、いってみましょう!
「慶應中等部の算数は簡単だから基礎・標準を徹底的に!」というアドバイスの功罪。
さて、塾や家庭教師の先生が中等部志望の生徒さんにアドバイスをするときによく聞くのが、
「慶應中等部の算数は難問は出ません!」
「基礎から標準レベルのオーソドックスな問題しか出ません!」
「だから徹底的に基礎を固めていきましょう!」
といった言葉です。(これが本当に多い。非常に多い。)
僕がこれまで指導してきた生徒さんの中にも、他の塾・家庭教師の先生に指導を受けていたけど直前期に助けを求めてきた場合に、このアドバイスをもらい、そしてそれに従って勉強する子がたくさんいました。
でもこれが本当によくないんです。とても厄介。
なぜなら、これらのアドバイスは算数が合格点に行くのを大きく妨げるからです。
これら3つのアドバイスは、慶應中等部の算数に精通していて、かつ一定の水準で合格者を出している先生の口から出ることはまずありません。慶應中等部の算数を表面的に見ていて、構造を全く分かっていないからこそできるアドバイスだからです。(別の表現で言うなら、「慶應中等部の先生たちが求めていること」を全く感じ取れていない、と言えるでしょう。)
どういうことか。説明します。
慶應中等部の算数の構造。
慶應中等部の算数ですが、年度によって多少の差はありますが、問題の難易度と配点の構成は基本的に以下のようになっています。
- 約70点分:基礎・標準レベル問題。
- 約20点分:思考力問題。
- 約10点分:ハイレベル問題。
上述のアドバイスをする先生は、慶應中等部の算数の大半(約70点分)が「基礎・標準レベルの問題」であることに着目して、「これが解ければ7割取れる!」と思っているんです。
でも、慶應中等部の合格最低ラインは7割ではありません。
合格最低ライン(1次合格者ではなく最終合格者の最低ライン)は約8~9割です。
また、僕がこれまで見てきた中で、慶應中等部に合格した生徒さんが過去問の算数を解いていた際の得点でいうと、基本的には9割~10割を取れることが多いけど、時にミスや時間不足で落としてしまって8割~9割になることが多いです。つまり、どれだけ落としても8割以上はキープできる子が実際に慶應中等部に合格するんです。
だから、中等部を目指すのであれば、算数は基本的に9~10割ラインを、最低でも8割ラインを目指すことが必須だと言えます。
でも、上述のアドバイスを受けて勉強する子は、スタート時点で7割を取ることが目標になってしまうんです。言い換えるならそれは、満点が7割になってしまっているようなものなんです。
「7割」は足切りのようなもの。勝負は「3割」の中にある。
要は、「7割」の問題はもはや足切りのようなものです。ここが取れるのは当たり前。
つまり、勝負は3割の中にあるわけです。慶應中等部の算数は、この「3割」の問題をどれだけ取れるかの戦いなんです。
それなのに、上述のアドバイスに沿った指導を受けていると、足切り点を取るためのような対策になります。これを小6の直前期まで続けている子が本当に多い。合格を目指す受験生たちが「3割」の問題と対峙して算数力を高めている直前期に、「7割」の問題とにらめっこしているわけです。
そしてそういった場合、たいていは直前期に過去問の点数が50点~70点の幅で上下し、「あれ、最低点に届かない!」「あともうちょっとなのに!」と焦り出し、転塾することや家庭教師を付けることを考え始めます。でも時すでに遅し。思考を要する「3割」の問題と対峙するための思考訓練が圧倒的に足りていないし、基本的な問題に慣れすぎていてハイレベルな問題に挑もうという気力・自信・根気もなくなっている場合が大半です。
だから、ちょっと語気を強めで言わせてください。
「慶應中等部の算数は簡単」というアドバイスは、真剣に中等部合格を目指す方は絶対に真に受けないでください!
慶應中等部の算数で合格点を取るための対策。
以上からも分かるように、慶應中等部の算数で合格点を取りたいのであれば、やることは明確です。
- 「2割」の思考力問題。
- 「1割」のハイレベル問題。
この2つを「日常的に」こなすことです。小6の夏以降に難しい問題の取り組み始める受験生は多いですが、それだと遅い。
小4・小5の段階から週に1・2問でもいいから、「難しい」と感じる問題にしっかりと向き合うこと。そういう問題に慣れることが大事です。もしすでに小6だとしたら、「1日1・2問」くらいのペースで難しいと感じる問題にしっかり取り組むようにしましょう。
くれぐれも、「7割」のための基礎・標準問題にばかり目を向けて、そこに慣れて、慶應中等部の算数の満点を勝手に70点に下げて、その満点70点を目指すような勉強はやめましょう。
どういう問題が「思考力問題」や「ハイレベル問題」なのかは、今後の記事で「年度ごとの過去問分析」を書いていく予定なので、それを参考にしてください。(1年ずつ更新していくので、少々お待ちください。)
また、より具体的な方法論についても次回以降に書いていく予定なので、中等部志望の方はぜひ読んでみて下さいね。(こちらももう少々お待ちください。)
慶應中等部算数の年度ごとの過去問分析
下記の記事では、慶應中等部の算数の年度ごとの過去問分析を行っており、各問題ごとの「内容・配点・難易度・時間配分(目安時間)」を書いています。
また、上述の問題分類に沿って、問題を以下の2つに分類しています。
- 約70点分の基礎・標準レベル問題を「7割問題」(足切り問題)
- 約20点分の思考力問題と約10点分のハイレベル問題を「3割問題」(合否を分ける問題)
この分類は過去問演習の際にかなり参考になると思うので、ぜひご活用ください。
慶應中等部2025年度(令和7年度)の過去問分析
慶應中等部2024年度(令和6年度)の過去問分析
(まもなく更新します。少々お待ちください。)
.
さいごに、慶應付属3中学の算数にオススメの問題集
最後に慶應付属3中学を目指すうえでオススメの算数の問題集を紹介しておきます。
「慶應3中学算数合格問題集」
(クロノクリエイト)
この「慶應中学算数合格問題集」は、慶應中等部・慶應普通部・慶應湘南藤沢3校で過去に出題された算数の問題を単元ごとに分けてあるのがオススメな理由です。単元ごとに重点的に学んだり、苦手分野の克服にとても有効なんですね。
単元ごとの学習が必要な方は、ご活用することを強くオススメします。
.
というわけで、今回はこのあたりで。
もしまた読みたいと思っていただけましたら、ブログのブックマーク、もしくは更新情報を投稿しているX(旧twitter)のフォローをよろしくお願いいたします。
【X(旧twitter)】
・ たくと@慶應付属中専門の塾講師・家庭教師
( @tact_roadtokeio )
ではでは、ご覧くださってありがとうございました。
また次回、お会いしましょう。